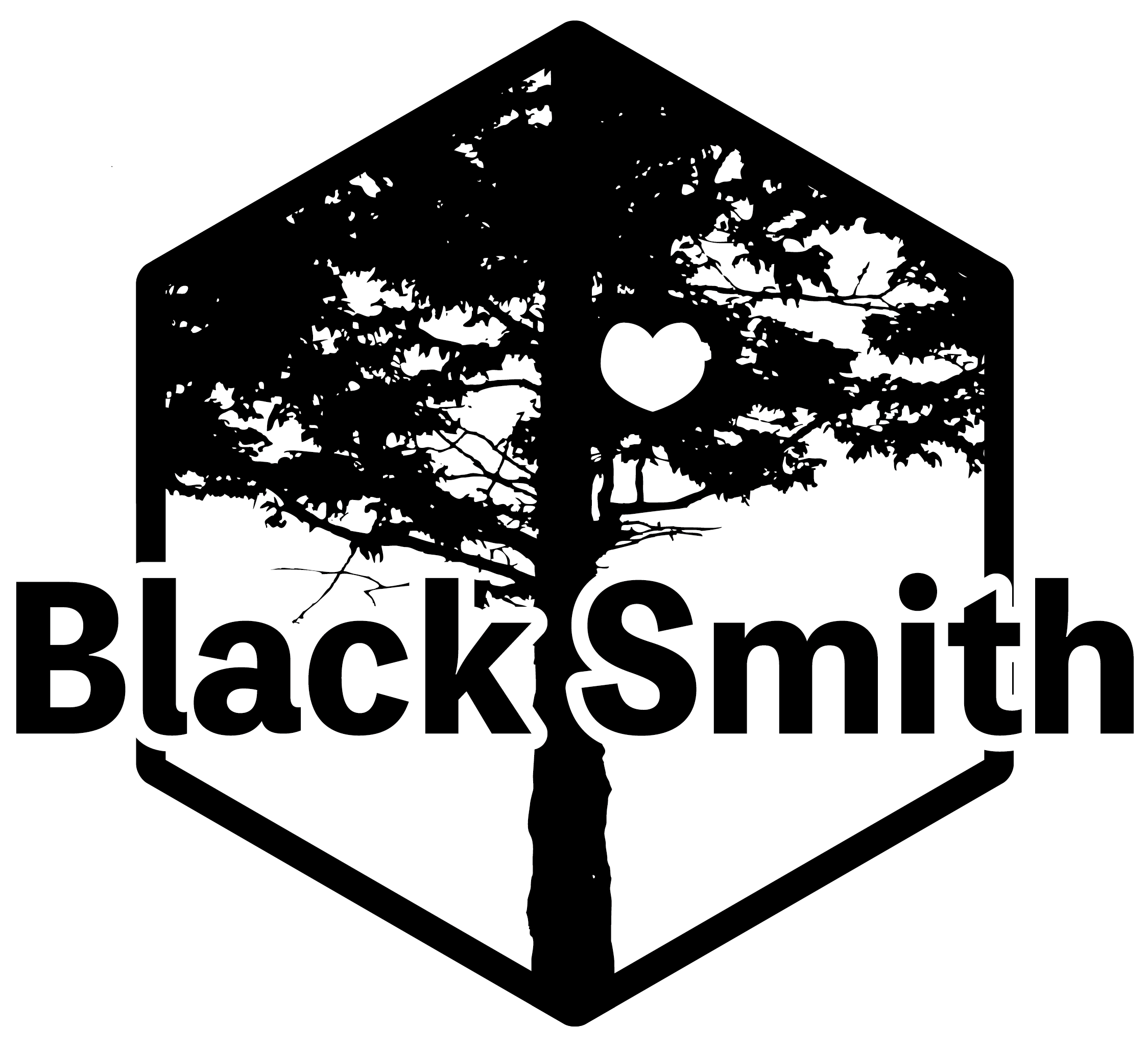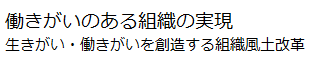理想の組織を考えてみた(個人編)
明けましておめでとうございます。
ブラックスミス株式会社 代表取締役の服部裕樹です。
新年初コラムとして、理想の組織を考えてみました。
私は今までワークライフバランスに始まり、働き方改革、組織風土改革、教育に係り、心理学や脳科学を学び多くの人のプロファイリングをしてきました。
また私自身も経営者として理想の組織を考えてきました。
組織の最小単位は個人ということで、理想の個人は、主体性が高く、チャレンジし、否定的な言葉ではなく、ポジティブな言葉を使い、視野が広く視座が高く、楽しんで仕事していて、上司の期待や指示の意図を理解して努力する人に行きつきました。
これらの能力は、『非認知能力』と言われます。
教育現場で使われる言葉になりますが、認知能力は、分かりやすく言うと、点数化しやすく点数で能力を測りやすい能力です。国語、算数、理科、社会などです。
非認知能力とは、点数化が難しく、テストなどで能力を測ることが難しい能力です。コミュニケーション能力、自己肯定感、自己効力感、創造力、相手の立場になって物事を考える力、レジリエンス、グリット、対話力、協調性、多角的な視点、視野の広さ、実行力、問題解決能力などです。
AIが著しい成長を遂げているこれからビジネスの世界でもこの非認知能力が重要視されるでしょう。
理想の個人が多い組織では、マネジメントにかける労力がかなり少なく済みます。一言でいうと、経営者も管理職も楽です。経営者や管理職が本来やるべき業務に専念できます。
個人が集まり、チームや組織になります。理想の組織は、新卒も含め離職率が低く所属意識が高く、効率が高く業績が安定し、会議では、意見や提案が出て、組織の目的、ビジョン、価値観に沿ってみんなが行動し、お互い感謝を伝え合っている組織です。
組織ごとに抱えている課題や問題も様々ですが、理想の個人が多く、理想の組織になれば、多くの課題や問題が解決されます。
物やサービスが溢れ、AIが急成長し、時代の流れがこれだけ速くなった現代、イノベーションを起こし、企業競争力を高め、会社を存続させるために、チャレンジに積極的になる必要もあります。
チャレンジに積極的な組織風土ができると、失敗しても隠さず、すぐに共有し、責任転嫁が起こらず、常に学び、その学びを会社へ貢献しようとして、風通しがよく、オープンに話し合う文化が根付き、チーム全員でチームをリードする組織となります。
理想の個人とは
*主体性が高く、チャレンジする
主体性が低い社員が多いと、組織の成長が停滞しやすくなります。なぜなら、主体性が低い社員は、往々に与えられた仕事をこなすだけで留まり、新しいアイデアを提案したり、自ら課題解決に取り組んだりすることが少ないためです。
また主体性の低い社員が多いと、優秀な社員にしわ寄せや負担が偏り、不満を感じやすくなります。結果、優秀な社員が離職するリスクが高まります。
組織が成長し続け、競争力を高めるためには、主体性の高い社員は必須となります。
*否定的な言葉ではなくポジティブな言葉を使う
否定的な言葉が多く社内で飛び交っていると、社内の雰囲気が悪くなります。
例えば、「できない」「無理だ」「どうせ失敗する」などの言葉が多く使われると、周りの社員のやる気も削がれます。また主体性が高くチャレンジできる社員は、否定的な言葉を嫌います。自分が何かチャレンジしようとすると「無駄だ」とか「失敗する」とか言われ、やる気の炎に水を差されるからです。
結果、主体性が高く優秀な社員の離職に繋がります。これでは、競争力を維持することは難しくなっていきます。
また人間の心理的に、何かを提案したりした時に、否定される経験を多く積むと、ここでは言っても無駄だという心理になり、意見や提案が出なくなり、結果的に、イノベーションが起こらない会社が出来上がります。イノベーションもまた競争力を維持するために重要な要素です。
*視野が広く視座が高い
視野が狭く視座が低い社員は、目の前の自分の仕事しか見えておらず、自分の仕事が何のためにあるのか、その仕事が周りに与える影響など考えず、どのように組織に貢献しているかを考えないです。
部分最適と全体最適という言葉がありますが、全体最適を考えることができません。結果的に部分最適になりがちです。
経営者や管理職であれば、全体最適を考えていると思いますが、視野が狭く視座が低い社員が多いと、全体最適の障害になります。
また目の前の自分の仕事しか見えていないので、組織の目的やビジョンに沿って行動することもできません。
これでは、経営者や管理職の負担が増すばかりです。
*楽しんで仕事をしている
やる気がなく嫌々仕事をしている社員は、生産性が低く、最低限の言われたことしかしません。仕事の質も低下し、ミスを増えることがあります。
社員が会社へ提供する価値と報酬が見合わず、利益率の低下の一因となります。
周りの社員のモチベーション低下や不満を招き、優秀な社員の離職につながることもあります。
また最低限の仕事しかしないため、イノベーションも起きず、競争力も低下し、会社を存続させることが難しくなります。
*上司の期待、指示の意図を理解して努力する
上司の期待や指示の意図を理解できない社員は、自分の仕事がなぜ必要なのか、会社のどう貢献するものなのかを考えません。結果、言われたことしかできない社員となります。
上司は細かな指示をしなくてはならず、指示するための時間が多く取られてしまいます。上司の時間を奪うことに繋がり、上司の生産性は低下します。
上司の中には、部下に細かく説明してやらせるより、自分がやった方が早いと考え、自分が仕事を多く抱えてしまう上司も増えるかもしれません。部下を持っている人であれば、一度はそのように考えたことがある人は多いのではないのでしょうか。
私も昔、部下に細かく説明してやらせるより、自分がやった方が早いと考え、自分が仕事を抱えたことがあります。今では、そのようなことはなくなり、自分のやるべき仕事に専念できるようになりました。
次回は、理想のチームについて書こうと思っています。
最後に、
自己肯定感、自己効力感、相互承認力が育まれた大人が一人でも多くなることを祈り願っています。
10人いれば、10通りの価値観や考え方があります。
そんな中、少しでも自分の考え方や価値観に共感した箇所があれば、あなたの中に取り入れてもらったり、SNSでシェアしてもらったり、周りの大切な人に伝えてもらえたら嬉しく思います。
今後、綴っていく内容は、あくまで自分の考え方や価値観に過ぎません。
盲目的に受け身になり、鵜呑みにしないように注意してください。
良い考え方なのか、そうでもない考え方なのかは、あなた自身の心で感じて、考えて、判断してもらえればと思います。
多くの人に伝わればいいなぁと思っていますので、ここに綴る内容は、転載、流用、改変、派生物いずれも自由です。
ただ誤解が広まらない様にだけ注意していただけたらと思います。